教員たるもの毎日出勤して生徒のことを考えなくてはならない。
休みを取るなんて言語道断。
あの先生また休んでいるんだって周りの迷惑を考えろよ。
そんな言葉が聞こえてきます。
今回のテーマは教員の休みの取り方です。
教員は公務員または会社員ですので、一般的な職業と同様に有給休暇取得の義務と権利があります。
ところが、教育関係者の話を聞くほどに【休みなんて全く取れない!】という声が聞こえてきます。
なかなか休みのとりにくい雰囲気があるみたいですね。
ひどい話ですが、年次有給休暇をズル休みなんていう教員もいるようで、とんでもないことだと思います。
今回は、教員が休むことについてまとめていきます。一方で、休みを取ることがどうしても難しい場合、もし生活が仕事で崩れているなら、以下のサービスを使って転職も検討してみましょう。
転職エージェントの利用は基本無料です!転職の際には必ず利用したい!
各エージェントごとに異なる強みがあるので、基本的に複数登録をおすすめします!
リクルートエージェント業界最大手で使いやすい!とりあえず登録しておいて損はない。求人豊富。
20代のための就職・転職支援【えーかおキャリア】20代の転職支援に特化し、未経験領域への転職支援も可能。
マンツーマンで指導してくれて安心感がある。
年次有給休暇は労働者の権利
まず年次有給休暇について簡単に説明します。名称が長いので、以下年休と称します。
年休は労働者の権利です。
日本企業は古くから年休の消化率が悪く、政府も最近年休を必ず年間で5日取ることを法律で定めました。
ちなみに年休を取らないと設置者である偉い人たちが労働基準監督局に指導されますので、絶対5日取れよなんて言われてないですかね。
このように最近は年休について比較的とりやすい雰囲気が出てきています。
また、年休は労働者の権利です。
年休の日は勤務日に当たる日であればいつでも労働者が自由に設定をできます。
年間の年休回数は20回ほどあり、使わないと繰越または自然消滅します。
なので積極的に年休を使ったほうがいいわけです。
年休取得の理由については管理職等に報告する義務はありません。
労働者の休養や余暇を目的としている制度ですから、休みがただ増えるだけ。
そして、年休の取得について、管理職や設置者が認めない、ということはできません。
取るといえば必ず取れます。なぜなら労働者の権利だから。
年休取得拒否などは法律違反です。
しかし、学校の先生の姿を見ていると、なぜか(年休なんて取れないよ・・・)という先生が多いですよね。
その理由も解説します。
教員が年休をとりづらい理由
僕の経験上、以下のような理由で年休は取れない!という先生は多いです。
クラス担任をしており代わりに診てくれる先生がいない
昨今、担任の先生がいないことが大きな問題としてニュースで取り上げられています。
担任は負担が大きく、なりたくない先生が多いのと、教員の数が不足しているのが理由です。
担任をしていると、毎日保護者連絡や生徒の健康、安全管理があり、なかなか休めないですよね。
副担任のような先生がいてくれれば良いのですが、教員不足ゆえに担任しかいない、という学校もありますし、副担任の先生はそもそも病休で休みがちな人が当てられていることもあります。
代打がいないので休めないわけです。
授業が進んでいないから
学校のカリキュラムは詰め込みが進んでいます。
正直、教科書を読んでいくだけでもなかなか内容が消化しきれないというのが実情。
授業に穴をあけてしまうと、カリキュラムマネジメントができなくなってしまうので休めないという先生もいらっしゃいます。
同僚からの陰口や心無い声
休みを取ると、敵視してくる同僚というのが一定数います。
あいつは平日の授業日に休みをとっている、おかしい。
俺は命懸けで教員やっているのにあいつはなんだ。
教員をやっている人は全員がまともなわけではなく、こうした『有給休暇というものがわからない』『仕事に命をかけていてそれを同僚にも強要する』ケースがあります。
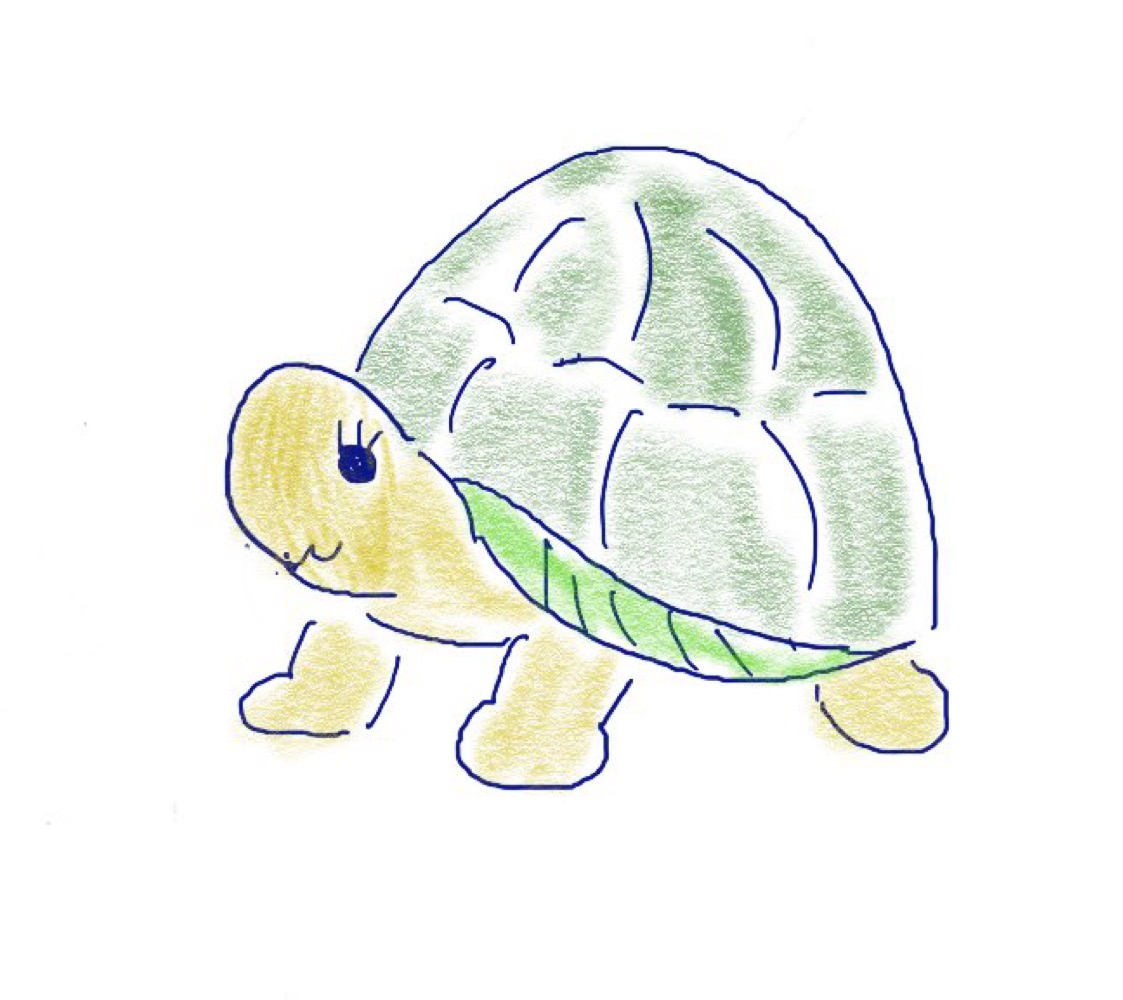
僕の同僚には同僚にもこういう人がいました。話にならないので無視して休みますが、教員も人間なので、こうした話の通じない人が一定数いるのです。
こうした異常な教員を管理職が管理できていなかったり、または管理職がこうした教員であるケースもあって、困ります。
教頭や校長に就任する人は、まともなコンプライアンス研修を受けてから就任してほしいものです。
年休を取る方法
さて、こうした雰囲気や人に負けずに年休を取得できれば良いのですが、業務は毎日続いて行く以上、その後の人間関係を考えると年休をとりにくい、ということはありますよね。
こうした場合、年休をうまくとっていく方法をまとめていきます。
1、割り切る
まずは割り切るということです。
先に述べた通り、年休の取得は労働者の権利です。
教員も休んでいい。
年休届を出して、あとは学年の主任や管理職に、「休むからよろしく」と言っておけば良いのです。
それでトラブルが起こった場合、それは校長の責任です。
なぜなら、年休取得者が不在の場合業務が円滑に進むよう取り計らうのは管理職の責務だから。
なので難しいことは考えず、「権利だから休もう」と割り切ることが重要です。
2、義務で取らなければいけないと口にする
もし周りの人間が「授業日に休むなんてとんでもない」と言ってきたら、「いや義務だから仕方ない」と逃げましょう。
設置者は、労働者に年休を5日取らせなければいけないと、決まっています。
教頭先生などに、「必ず休んでくれ」と言われた人も多いのでは。
それを逆手にとって、「休まなくちゃいけないんだよ〜」と適当に誤魔化しておきましょう。
管理職が言うんだから仕方ないよなーと、管理職や偉い人のせいにしておけば良いのです。
3、年間の中で業務量を計画しておく
最後は自分の仕事を年間でマネジメントして行くと言うことです。
教員は仕事量が膨大で自転車操業になりがちですが、多くの場合「要求されている以上の仕事をやりすぎている」のです。
仕事は5割から8割で完成させ、回して行くことが重要です。
なんでも完璧にはできないですし、コピペで済むならそれで良いと思います。
すると、業務の中にも重みがあり、重要なこととそうでないことをわけ、重点的に時間をかける日とそうでない日を作っていくことができます。
そうした空きを作ると、結果として休みやすくなるわけです。
僕は今まで担任業務や主任業務をこなしてきましたが、タスク管理ができれば潰れたり休みが取れなくなることはないと断言できます。
教員こそ、自分のマネジメント方法を学ぶべきです。
僕はその方法を読書で身につけました。
自分の周りの残業が常態化していたり、仕事の遅い人を参考や目標にしてはいけません。
僕がノウハウを学んだ本は以下に紹介しています。
特に若手の先生にこそ読んでいただきたいものを厳選しています。
それでもダメなら教員なんて続ける必要がない
例えば、有給の取得を邪魔したり、残業や業務の削減に積極的でない管理職の姿が目に入るとします。
あなたは将来その人のように働きたいですか?
あなたの所属した学年の先生の姿を見て、学校て嫌だなと思いますか?
僕は一度、ずっとこのはtらき方が続くのか?と考えたら嫌になって、教員から転職しました。
転職というのは、一つの選択肢だと思います。
転職をすると、一般的には給与が下がります。
世の中にはパーフェクトな職場なんてなくて、転職したって幸せになれるとは限りません。
しかし、一度転職してみると、「自分の悩んでいたことは大したことではない」と気づきを得ました。
僕は転職後、3年ほど営業の仕事をして再び教員に戻りました。
フリーランスのように、複数の学校の非常勤として、リハビリのように1年働き、今また担任も持ってフルで働く教員に戻りました。
すると、「自分で変えられることは思いのほか多いぞ」と感じました。
僕と同じように、教員から転職した人。
他企業から教員に転職した人。
教員を一度やめて、僕のように教員に戻った人。
いろんなパターンがありますが、もし働き方で迷っているのなら転職するのは一つの手です。
明らかに世界が変わりますし、世の中いろんな方法で食っていけるんだなと思えます。
転職をする場合、下記の転職エージェントを必ず利用しましょう。というのも求人の多くが非公開求人で、そもそも発見が難しいからです。
転職エージェントは非公開求人の取り扱いや転職面談、履歴書添削などを全て無料で受けられるので、必須のサービスなのです。
転職エージェントの利用は基本無料です!転職の際には必ず利用したい!
各エージェントごとに異なる強みがあるので、基本的に複数登録をおすすめします!
リクルートエージェント業界最大手で使いやすい!とりあえず登録しておいて損はない。求人豊富。
20代のための就職・転職支援【えーかおキャリア】20代の転職支援に特化し、未経験領域への転職支援も可能。
マンツーマンで指導してくれて安心感がある。
僕の転職の体験談や、転職方法を以下の記事にまとめています。
教員を辞めるかどうかは人それぞれですが、今はずっとその職場にしがみつかなくてはいけない時代ではないと思います。
年休は取ろう
僕は年休とります。
苦情が来ても授業遅れても、うまくマネジメントして年休をとることが、自分のためになると知っているからです。
休日が増えると、その分自己研鑽ができます。
家族と触れ合う時間も増えます。
結果的に自分の人生が充実する気がします。
世の中には年間休日が140日くらいある会社もあるそうで、そういった会社は充実するだろうなと思います。
人それぞれ、置かれた場所で生きていくしかありません。
けれど、自分でいくらでも身の置き方や働き方、考え方は変えることができますよ。





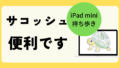
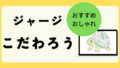
コメント